著者:菅原慶乃
出版社:晃洋書房
発行年月:2019年7月
中国で最も早く映画が輸入されたのは上海だと言われる。1920年代の上海で「途中入場お断り」、「鑑賞中はお静かに」などの映画鑑賞マナーがすでに出来上がっていた…と聞くと、ちょっと意外な感じがする。初期の映画館では観客が自由に飲食したり弁士に声をかけたり拍手や野次を飛ばしたりと、猥雑な鑑賞風景だったイメージがあるからだ。
19世紀末から1930年代までの上海初期映画界において、映画鑑賞マナーがどのように形成され浸透していったのか。それを観客の側から実証的に跡付けたのが『映画館のなかの近代 映画観客の上海史』である。単に鑑賞マナーだけでなく、「映画の観客」というものが、近代化の進む民国期上海においてどのように作られていったのかを明らかにしている。著者の用語で言えば「ヴァナキュラー・モダニズム」(通俗的近代化とでも訳せばいいのだろうか)の思考だ。
著者は、「映画観客」というものが自然発生的に生まれたものとは考えない。それは「国民」、「民族」、「ジェンダー」などと同じように「近代以降規定された」新しい集団である。「(映画観客とは)映画が上映される場所にアプリオリに存在する集団ではなく、映画鑑賞という文化規範の実践を通じてパフォーマティヴに創出されていったものであった」(終章)と著者は言う。そして「パフォーマティヴに創出」した主体が、五四新文化運動以後の上海の大衆エリートたちによる映画ジャーナリズムであったことを明らかにしていく。
だが面白いのは、この「映画観客」の創出が直線的な右肩上がりの「進歩」だったという従来の「発展史」を、著者が繰り返し否定していることだ。例えば「田舎vs都会」「伝統vs近代」といった二項対立による安易な社会進化論的見方では観客史の実態はつかめないというのだ。当時の上海において「「伝統」的な遊興と映画興行は本質的には連続するものだった」と著者は述べる。
その証左として著者が持ち出すのが「遊歩」という習慣である。習慣というよりもライフスタイルの一部というべきか。当時上海の繁華街には「茶園」や「遊戯場」と呼ばれる一大アミューズメント施設が多々あり、さまざまな見世物やショウが繰り広げられていた。都市生活者たちは休日や仕事帰りにそれらへ立ち寄り、暇つぶしや劇場へ観劇に行くまでの時間つなぎに「遊歩」をして楽しむ。その中で、新しい見世物の一つとしての「映画」に人々は出会った。
幻灯上映の流行などで映像文化にすでに馴染みのあった上海人にとって映画は格別の驚きをもたらさなかった。映画はわざわざ時間を決めて観に行くものではなく、遊歩の途中で回遊的に目にするものだったのだ。さらに、伝統的な演劇の観客と映画の観客が「遊歩」によって重なり合っていた。それが結実した作品が、現存する最古の中国映画フィルム『労働者の恋』だと著者は言う。
『労働者の恋』(労工之愛情 1923 『八百屋の恋』の別題あり)の存在はわたしも以前から知っていた。この作品は典型的な(すなわち欧米的な手法で作られた)無声喜劇であるとわたしは見ていて、かつて中国でかように「ベタ」なドタバタ喜劇が作られていたことに親近感を感じていた。
著者は第一章で『労働者の恋』についてやや詳しい分析を加えている。この映画が米国式ドタバタ喜劇の習作であると同時に、上海の演劇で当時流行していた「機械布景」という舞台装置を取り入れるなど演劇と映画のクロスジャンル的作品として作られているという著者の見立てはとても興味深い。
本書では触れられていないが、主人公の八百屋が恋する女性との結婚を許してもらうため、彼女の父が営む医院を儲けさせるべくケガ人を「大量生産」するというプロットは、ハロルド・ロイドの短編『落胆無用』(Never Weaken 1921)にそっくりである。また、「機械布景」が取り入れられているとおぼしき「階段ギャグ」はバスター・キートンの短編『化物屋敷』(The Haunted House 1921)の階段セットを思わせる。
『労働者の恋』はそれら同時代のアメリカ喜劇の強い影響下で作られたのではとわたしは推測しているが、路地や家のセットだけで撮影されているなど演劇的なニュアンスがあるのも確かだ。著者の言う「遊歩」文化と重ね合わせることで、このチャーミングな喜劇映画の違った側面が見えてきて、興味は尽きない。
他には、作品の梗概などをこと細かく書き記した「映画説明書」の存在(第二章)や、外国映画の中間字幕を自主的に訳して「解説」するお節介な観客(第三章)などが紹介される。当時の上海の映画館の雰囲気が色と形を持って立ち現われてくるようで、映画ファン(映画館ファン)にはたまらない。上海の映画館は当時すでに座席指定制だった、中国語字幕を幻灯で投影する技術があった、トーキーになると同時通訳風のイヤフォンが開発されて「イヤフォン嬢」なる職業が生まれた…などなど、その「モダニズム」ぶりには驚かされる。
本書の後半では、「遊歩」文化の散漫な映画鑑賞のあり方が、外国で教育を受けた教養人たちの言説によって変質させられてゆく過程が論じられる。例えば映画に教育的価値を見出した上海YMCAと商務印書館の映画制作部が果たした役割や、当時の上海を覆っていたセンセーショナリズムの問題(三面記事、「黒幕小説」の隆盛、実録犯罪物映画の大ヒット)とそれが必然的に引き起こす取締強化などだ。さらには反帝国主義ナショナリズムの高まりによって、前近代的で猥雑な映画鑑賞のあり方はしばしば問題にされた。「良き観客」になることはすなわち「良き国民」になることだという文化的コードが醸成されてゆく。
それにしても著者がその醸成のプロセスをあくまで実証的に示そうとする努力には頭が下がる。白眉は第六章「映画館への通い方」だ。著者は上海で活動した陸澹安という文化人の1910〜40年代の日記を丹念に読み込み、徹底した調査によって映画鑑賞行動の変質を跡づける。あまり知名度のない陸澹安という人物を著者があえて選んだ理由の一つは、彼の映画鑑賞が知的エリートとは違う、よりヴァナキュラーなものであるからだ。
とはいえ、著者が補足的に紹介している高名な小説家・郁達夫の日記には、やはり心を揺さぶられた。1927年3月21日、ゼネストで戒厳状態にある上海を、若き郁達夫は恋人と共に彷徨い、北京大戯院に逃げ込んでダグラス・フェアバンクスの『バグダッドの盗賊』を観たという。混迷する現実からファンタジックな映画の世界へ逃避する上海の若い恋人たち…まるでそれ自体が映画のワンシーンのようだ。
この逃避場所としての映画館の概念を、著者はフーコーを援用して「ヘテロトピア」と呼ぶ。「映画館は、文字通り武力的脅威からの避難場所であり、現世のきな臭さと併存しながらもそれとは全く異なる世界が展開するヘテロトピアだった」(第六章)。多くの映画が自己言及的に繰り返し描いてきた「ヘテロトピア」としての映画館は、上海においては大衆エリートたちの政治的意図と分かち難く結びついていた。そしてそれは東アジア全域において共通したプロセスではないかと著者は述べている。
だが、「ほんの百年ほど前を生きた人びとのささやかな生活の細部、とりわけ遊興や娯楽にかんする実態の把握を困難にするのは、それを実証する資料がほとんど無いということに尽きる」(第六章)と著者は嘆く。さらに実証資料のなさに輪をかけて、女性や子どもの鑑賞行動を追う難しさにも言及している。
しかし、当たり前だが、百年前の上海で映画を観ていたのは成人男性ばかりではない。わたし自身、日頃上映会や映画祭に関わったり、また在野研究者の立場で「ファンダム」の存在に魅力を感じている身としても、観客としての女性と子どもの存在価値はひしひしと感じている。研究の困難さは素人目にも明らかだけれど、今後この方面の調査が進むことを大いに期待している。
(いいを じゅんこ/クラシック喜劇研究家)

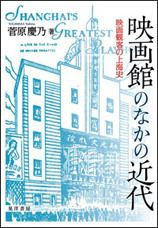 「映画館のなかの近代 映画観客の上海史」
「映画館のなかの近代 映画観客の上海史」