『映像の発見=松本俊夫の時代』 筒井武文監督インタビュー

第7回神戸ドキュメンタリー映画祭「松本俊夫特集」の主軸となる、『映像の発見=松本俊夫』五部作。戦後日本の映像表現を進化・拡張させてきた作家の半世紀に及ぶ軌跡を、筒井武文監督が11時間40分のドキュメントにまとめ上げた注目作だ。松本俊夫の越境的な活動に沿うように複数のアプローチを持つ本作は、個人史だけでなく、様々な〈歴史─時代〉を浮き彫りにする試みでもあるだろう。13年越しで完成させた作品について筒井監督に訊いた。
──『映像の発見=松本俊夫の時代』五部作の制作の発端からお聞かせください。
鈴木達夫キャメラマンのドキュメンタリーを撮ることになり、その監修をお願いしたくて松本俊夫さんにお会いする機会がありました。そのとき伺った松本さんの話があまりに面白くて、記録したい欲望が芽生えた。それが2003年で、最初に撮ったのが第Ⅰ部「記録映画篇」のインタビューです。そこでは松本さんの映画との出会いから、映画界に入ったのち、記録映画の時代を中心に『母たち』(1967)の制作までを追っています。
──五部構成の構想は制作初期からあったのでしょうか。
取材を重ねるなかで発見することが多く、そこから全体の構成も出来上がっていきました。
遡ると、松本さんのインタビューで一本(『自分自身による松本俊夫』)、他の方々による松本さんについてのインタビューで一本(『他者による松本俊夫』)、それぞれ2時間で合計4時間の二部作にしようと考えていた時期もありましたね。それを経て三部作にしようとして、そのあと四部作、最終的に五部作に落ち着いた。撮影と研究とを始めてから認識したのは、「松本俊夫を描く」ことは、彼だけを描くのではないということ。映画、映像、環境芸術、現代芸術……とジャンルをはみ出しながら、戦後の日本映画史のあらゆる領域を横断・開拓した方です。松本さんの出発点は記録映画ですが、その後、体育館の中に浮かばせた風船に幾つもの映像を映写するといった、ほとんどパフォーミングアートのようなことも先駆的になさっています。CM、それから劇映画も撮るし、実験映画の草分け的な存在でもありますよね。「映像作家」と名乗ったのも松本さんが最初です。新しいメディアが生まれると、メーカーが松本さんにテストを依頼したそうです。
──批評家としての顔もお持ちです。
 政治的な意識も高く、世界の重要な作品を評価しようと啓蒙もされていた。特に第一評論集『映像の発見──アヴァンギャルドとドキュメンタリー』は伝説的名著で(三一書房、1963年、清流出版より2005年復刊)、後進の映画作家に大きな影響を与えた。蓮實重彦さん以前に最大の影響力を持っていた批評家でもあるわけです。『記録映画』、『季刊フィルム』、『イメージフォーラム』などの編集やメインライターもつとめて、いろんな論争もなさった。幅広くて奥深い松本さんの全体像を描くことで、日本映画史だけでなく、戦後の日本の歴史まで見えてくる。そういう稀有な存在であることにあらためて気づかされました。
政治的な意識も高く、世界の重要な作品を評価しようと啓蒙もされていた。特に第一評論集『映像の発見──アヴァンギャルドとドキュメンタリー』は伝説的名著で(三一書房、1963年、清流出版より2005年復刊)、後進の映画作家に大きな影響を与えた。蓮實重彦さん以前に最大の影響力を持っていた批評家でもあるわけです。『記録映画』、『季刊フィルム』、『イメージフォーラム』などの編集やメインライターもつとめて、いろんな論争もなさった。幅広くて奥深い松本さんの全体像を描くことで、日本映画史だけでなく、戦後の日本の歴史まで見えてくる。そういう稀有な存在であることにあらためて気づかされました。
──第Ⅰ部だけでも、かなりの厚みがあります。50年代から60年代までの松本さんの歩みを一望できるつくりです。
松本さんは映画界入りして、新理研映画で助監督を経て監督になり、組合運動で委員長をやって自分だけがクビを切られてしまった。1959年の頭からフリーとして活動を始められますが、スポンサーを逆撫でするような映画をつくって、どんどん仕事を失っていく。映画を撮れなくなり、シナリオを書いたりテレビ作品を制作するものの、そこでもまた局を激怒させて出入り禁止になる。ラジオもそうですね。その後、演劇を手掛けるとヒット作を生み出した。しかし、舞台演出家としての才能を持ちながらも、映像へのこだわりから断念してしまう。63年から67年には映像作品をまったくつくらない空白の時期があります。あらゆる仕事をして食いつないでいたという、いまではちょっと信じられないエピソードも。それが、『母たち』で第18回ヴェネツィア国際記録映画祭のグランプリを獲って復活なさる。その一部始終が第Ⅰ部。五部作のなかでも最も山あり谷あり、ハッピーエンドで楽しめる構成です。
──最後に松本さんに向けられる質問とその答えも粋だと感じました。そこから13年越しで大作を仕上げられたのは、松本さんへの敬愛のなせるところでしょうか。
 いや逆に、昔から敬愛していて直接交流のあった方──たとえば吉田喜重監督──が相手でしたら、こういった作品は作らなかった。実は、僕の記録映画時代の先生である渡辺哲也さんは松本プロの方で、その系譜では僕は松本さんの孫弟子にあたるとも言えるんですが、お目にかかってお話を伺ったことは一度もなかった。ものすごく好きな作品もあれば、そうでないものもあったしね。すべてを好きなファンではなかった。こういうドキュメンタリーを撮るための距離として、それがとてもよかったと思いますね。松本さんは芸術至上主義で「娯楽作は撮らない」と頑固におっしゃっていたけど、娯楽・商業的な作品を撮れる技量を十分お持ちで、それを行使しないのは非常にもったいないと僕は思っていたんです。『修羅』(1971)などは劇映画の作り手がこんなに緻密な演出をできるだろうかという見本のような作品ですし、『ドグラ・マグラ』(1988)も芸術映画といえばそうだけど、あれほど巧妙にまとめられるのは松本さんしかいないですよね。松本さんはCMやお金のためにやった仕事をあまりよくおっしゃらない。でも、それらがいかに素晴らしいかを松本さんに伝えたいというのも、まったく僭越ながら、僕の最初の動機のひとつでした(笑)。大学で実直に教育者として活躍している姿、厳格で見事な批評を書く姿だけではない人物像を伝えたかったし、お話がなにしろ面白い。松本さんを語る方たちのインタビュー──なかには愛情を込めて悪口を言う方もおられます──とカットバックすると、松本さんの真面目な口調が反転するんです(笑)。
いや逆に、昔から敬愛していて直接交流のあった方──たとえば吉田喜重監督──が相手でしたら、こういった作品は作らなかった。実は、僕の記録映画時代の先生である渡辺哲也さんは松本プロの方で、その系譜では僕は松本さんの孫弟子にあたるとも言えるんですが、お目にかかってお話を伺ったことは一度もなかった。ものすごく好きな作品もあれば、そうでないものもあったしね。すべてを好きなファンではなかった。こういうドキュメンタリーを撮るための距離として、それがとてもよかったと思いますね。松本さんは芸術至上主義で「娯楽作は撮らない」と頑固におっしゃっていたけど、娯楽・商業的な作品を撮れる技量を十分お持ちで、それを行使しないのは非常にもったいないと僕は思っていたんです。『修羅』(1971)などは劇映画の作り手がこんなに緻密な演出をできるだろうかという見本のような作品ですし、『ドグラ・マグラ』(1988)も芸術映画といえばそうだけど、あれほど巧妙にまとめられるのは松本さんしかいないですよね。松本さんはCMやお金のためにやった仕事をあまりよくおっしゃらない。でも、それらがいかに素晴らしいかを松本さんに伝えたいというのも、まったく僭越ながら、僕の最初の動機のひとつでした(笑)。大学で実直に教育者として活躍している姿、厳格で見事な批評を書く姿だけではない人物像を伝えたかったし、お話がなにしろ面白い。松本さんを語る方たちのインタビュー──なかには愛情を込めて悪口を言う方もおられます──とカットバックすると、松本さんの真面目な口調が反転するんです(笑)。
──第一部の終盤もそうですね。
ベトナム戦争中に、ベトナムで『母たち』のロケをして取っ捕まるエピソードですね。観光客を装って隠し撮りをしていたけど強制送還されて、羽田空港に着いたとき、松本さんがプロデューサーの工藤充さんに向けて、「一日しか遅れなかったぞ!」と言う。要するに、予算と撮影期日を守ったというのが第一声(笑)。それをお二人から別の角度で語っていただいて、カットバックすると面白くなるんですよ。編集した僕の「罪」でもあるんだけど(笑)。そういう面白さも伝えたかったから、ある意味ではコメディ映画として撮ったつもりもあります。5年くらい前だったでしょうか、五部作になる前、8時間ほどにまとめたヴァージョンを1日かけて松本さんに見ていただきました。松本さんに対する好意を含めた皮肉や悪口に怒り出すんじゃないかと冷や冷やしていたんですが、恐る恐る感想を伺ってみると、「これは筒井さんの作品なので、ここを使ってくれ、カットしてくれとは一切言いません。あなたの判断にお任せします」とおっしゃってくださった。自分への悪口も受け入れられる方で、そういう懐の深さも松本俊夫像の一面です。過去に激しい論争も繰り広げてきて、罵倒することもあったけど、相手のこと自体は認めているわけです。そのお人柄には感銘を受けました。
──続く第Ⅱ部が「拡張映画篇」です。
拡張映画、エクスパンデッド・シネマとはつまり、3面マルチや不定形の巨大映像など、映画館のスクリーンに収まらない映像体験ですね。第Ⅱ部では、その歴史も深めながら描いています。『つぶれかかった右眼のために』(1968)は日本初の本格的な3面マルチ作品ですし、頂点をなすのが1970年の大阪万博の「せんい館」の『スペースプロジェクション・アコ』。これは、僕が中学1年生のときに万博に行って見ていた。いまだにあの奇妙な映像体験は僕のなかに強く残っています。ディレクターの名前は意識していなかったけど、松本さんの作品を見たのは、おそらくそれが初めてだったと思うんです。その頃はCMもいっぱい撮られていた時期なので、無意識的には見ているはずですが。
──そして第Ⅲ部は「劇映画篇」。
第Ⅲ部では、周辺の方たちのエピソードを絡めて、わずか4本しか撮られていない劇映画への思いをお聞きしました。収録場所はアオイスタジオという録音スタジオ。驚いたのは、長くなるといけないので、「4作品を1本ごとに15分にまとめて、成り立ちから内容まで話していただけませんか」とお願いしたら、これがものの見事に4本とも15分ぴったり。それも論理的に語られるんですよ。「この人の脳内はどうなっているの? 精密なコンピューター!?」って、もう唖然としました。そのあと僕が追加でお話を訊いていくのですが、基本的なことはその15分にきっちり収められている。他の方の証言も交える必要がありましたので、15分すべては使えなかったんですけどね。
──松本俊夫さんというと実験映画を思い浮かべられる方が多いかもしれませんが、第Ⅳ部がその「実験映画篇」です。
 1960年代の終わりから70年代にかけて、16ミリフィルム、ヴィデオ、スキャナーなど特殊な機材を使って、毎年実験的な作品をつくっておられた時代があります。第Ⅳ部では、松本さんの作品をスクリーンに投影し、それをバックに語っていただきました。松本さんの身体にも映像が投影されています。松本さんの目の前のモニターにスクリーンと同じ映像を映して、それをご覧になりつつ話される松本さんの言葉と背後の映像とがシンクロするようにしました。
1960年代の終わりから70年代にかけて、16ミリフィルム、ヴィデオ、スキャナーなど特殊な機材を使って、毎年実験的な作品をつくっておられた時代があります。第Ⅳ部では、松本さんの作品をスクリーンに投影し、それをバックに語っていただきました。松本さんの身体にも映像が投影されています。松本さんの目の前のモニターにスクリーンと同じ映像を映して、それをご覧になりつつ話される松本さんの言葉と背後の映像とがシンクロするようにしました。
──ということは、画面上で2つのタイムラインができていることになりますか。実験映画的なアプローチですね。
「記録映画篇」は、普段お仕事されている場所で普通のインタビューふうに撮りましたが、ここでは別の方法を採りました。ジャンルごとにインタビューの場や環境を変えています。僕もそれくらいはやらないと(笑)。面白いのは、形式的な実験作品にも、松本さんの内面が結構投影されていること。全体の流れを追っていくと、それが見えてくるんですね。『ドグラ・マグラ』の公開が1988年。それに付随する実験作品もふくめて、そのあたりからは松本さんが自分自身を撮影対象にしていく。くわえて、あの頃はベルリンの壁が崩れ、ソヴィエト連邦も崩壊した時期。松本さんは初期の50年代から60年代には、安保闘争の記録のように、日本の社会と政治に焦点を当てていました。そうしたアプローチが今度は実験映画のなかに入ってくるんです。いろんなジャンルで表現していたものが、ふたたび記録映像に戻ってくるという面白いサイクルがあるんですよね。
──まさにジャンルとメディアを横断された方ですね。
第Ⅰ部の冒頭には、2006年に川崎市市民ミュージアムで松本さんが映像を使ったインスタレーションをおこなっているドキュメントを置いています。その解説映像が第Ⅳ部の最後に出てくる。つまり、第Ⅰ部から第Ⅳ部にかけてそれが完成していき、そこで完結するという構成上の流れがあります。本当はそれで終わるはずだったんですけど……。
──ひとつのサイクルが閉じた後に、第Ⅴ部「映画運動篇」が来ます。
 映画をつくりながら勉強していたことが多くて、その折々のインタビューでは僕の認識が至っていない、把握できていない事柄があったんですね。たとえば松本さんの万博参加。「反万博」の運動もわき起こり、日本の前衛芸術が、万博に参加する人と反対する勢力とに二分された。松本さんは万博反対派から徹底的に叩かれたのですが、いまの時点でそのことをどう思っているのか。そういった訊きそびれていたことを最後に追加でインタビューしました。それが松本さんのご自宅が取り壊される直前の頃。書斎で最後のインタビューをおこないました。第Ⅳ部までは自分の声を使うつもりはなかったので、ワイヤレスマイクは松本さんにだけ。僕の声も多少拾っていますが、必要ないと思っていました。でもここだけは自分の声も重要だと思って、僕自身もワイヤレスマイクを付け、真剣勝負で挑んだのが「映画運動篇」。ご自身の作品をつくる一方、いろんな映画に対して意見を発表し、論陣を張って、旧世代と戦った松本さんの「運動」を、現在の位置から総括してもらいました。大それたことでもありますが、それが第Ⅴ部です。
映画をつくりながら勉強していたことが多くて、その折々のインタビューでは僕の認識が至っていない、把握できていない事柄があったんですね。たとえば松本さんの万博参加。「反万博」の運動もわき起こり、日本の前衛芸術が、万博に参加する人と反対する勢力とに二分された。松本さんは万博反対派から徹底的に叩かれたのですが、いまの時点でそのことをどう思っているのか。そういった訊きそびれていたことを最後に追加でインタビューしました。それが松本さんのご自宅が取り壊される直前の頃。書斎で最後のインタビューをおこないました。第Ⅳ部までは自分の声を使うつもりはなかったので、ワイヤレスマイクは松本さんにだけ。僕の声も多少拾っていますが、必要ないと思っていました。でもここだけは自分の声も重要だと思って、僕自身もワイヤレスマイクを付け、真剣勝負で挑んだのが「映画運動篇」。ご自身の作品をつくる一方、いろんな映画に対して意見を発表し、論陣を張って、旧世代と戦った松本さんの「運動」を、現在の位置から総括してもらいました。大それたことでもありますが、それが第Ⅴ部です。
──その意味での「映画運動」なんですね。
ええ。文学者の全集に喩えれば、付録的な一冊、補巻的な作品といえます。松本さんの処女作は『銀輪』(1955)。これは松本さんが実験工房と組んで、音楽は武満徹さん、美術を山口勝弘さんが手掛けておられます。円谷プロとも共同制作したという伝説の映画ですが、2003年の時点では失われた映画、永遠に見ることのできない作品と思われていました。だから当初は松本さんの記憶だけで語っていただいたんですが、その後、ネガが発見されて見られるようになった。第Ⅴ部の最後では、発見の経緯についてお話しいただきました。それもまた、この映画の完成が遅れたこと、時間差の効用かもしれませんね……。松本さんはそのときに円谷英二さんに大変に気に入られて、円谷プロに誘われたんですよ。円谷プロまで行かれて悩まれたそうですが、結局は断った。そうしたエピソードも第Ⅴ部では語られます。僕は松本さんが監督したゴジラ映画を見たかったな(笑)。
──ご自身の映画には絶対出ない、メイキングでさえ「インタビューは厳禁」の筒井監督がワイヤレスを付けて取材されていることからも、第Ⅴ部が真剣勝負であることがうかがえます。
第Ⅴ部には、2011年にアテネ・フランセ文化センターでおこなった松本さんと僕のトークも入っています。僕の特集上映最終日に、トーク・ゲストとして登壇されたときのもので、この撮影が鈴木達夫さん。手持ちで会場を動き回りながら撮って、しかもそれが観客の邪魔になっていないという名人芸です。それで、編集に必要であろうというカットを全部撮られているんですよ。ここでの真の主役は「透明人間」の鈴木さんとも言えます。だから、絶対に映画には出ないという主義を破って僕も出演せざるを得ませんでした。その映像を使わないと、つながらないですからね。でも必要最小限。撮影が鈴木達夫さんでなければ、決して使わなかったと思う(笑)。
──つなぎといえば、松本さんの作品映像を編集されるときにどんなことを感じておられたでしょう?
不思議なのは、引用するときに、僕に編集されるのを作品が待っていたような印象を受けたことです。つまり、僕が決めるのではなくて、松本作品の手の上で僕が踊らされていると言ったらいいのか。
──ここまでお話を伺うと、やはり筒井監督が松本さんを敬愛しておられるのだなと感じます。
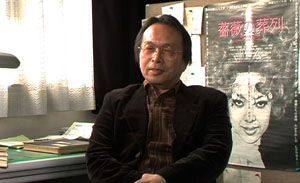 ……はい。ただ、すでにお話ししたように、はじめから大好きだったというわけではないんですよ(笑)。松本さんの作品を見直したり、お話を伺っていくなかでだんだんファンになっていたんです。川崎市市民ミュージアムでインスタレーションを制作されている合間の休憩時間に、たまたま話が始まって、キャメラマンが急いで撮ってくれたものが、出来上がった映画にも残っています。松本さんの映像作品に対する僕の回想から始まって、即興的に会話が広がっていった。そこはノーカットで使っています。リチャード・リンクレイターが、『6才のボクが、大人になるまで。』(2014)を12年かけて撮ったじゃないですか。リンクレイターはそのあいだ、他に何本撮ったのかな……、8本か9本でしょうか、並行して撮っていましたよね。その意味では僕も13年間撮りながら、そのあいだにつくった映画に松本さんの影響を受けているのかもしれません。松本さんの作品って、虚実を引っくり返すところがある。「ここは真実でここは虚構だ」という虚実を反転させたり、境界線を曖昧にする。それをいろんな形でなさっているんですよね。僕の映画づくりに、意識的にも無意識的にも影響していたのは認めざるを得ないですね。
……はい。ただ、すでにお話ししたように、はじめから大好きだったというわけではないんですよ(笑)。松本さんの作品を見直したり、お話を伺っていくなかでだんだんファンになっていたんです。川崎市市民ミュージアムでインスタレーションを制作されている合間の休憩時間に、たまたま話が始まって、キャメラマンが急いで撮ってくれたものが、出来上がった映画にも残っています。松本さんの映像作品に対する僕の回想から始まって、即興的に会話が広がっていった。そこはノーカットで使っています。リチャード・リンクレイターが、『6才のボクが、大人になるまで。』(2014)を12年かけて撮ったじゃないですか。リンクレイターはそのあいだ、他に何本撮ったのかな……、8本か9本でしょうか、並行して撮っていましたよね。その意味では僕も13年間撮りながら、そのあいだにつくった映画に松本さんの影響を受けているのかもしれません。松本さんの作品って、虚実を引っくり返すところがある。「ここは真実でここは虚構だ」という虚実を反転させたり、境界線を曖昧にする。それをいろんな形でなさっているんですよね。僕の映画づくりに、意識的にも無意識的にも影響していたのは認めざるを得ないですね。
──本作のサウンドデザインは、『孤独な惑星』(2010)も手掛けられた森永泰弘さん。これも楽しみです。
森永君には、裏テーマの構築を頼みました。『孤独な惑星』のように、もうひとつの物語を作ってくださいと。
──クレジットには映画批評家の方々のお名前も見られます。
第Ⅴ部のプロローグは、それまでの8時間版をご覧になった松本さんの話が入って来ます。まだその時は長大な一本だったわけですが。でも作品の中に作品批評が入るのは、松本俊夫的でもありますからね。そこで構成上、必要な人として中条省平さん、西嶋憲生さん、そして金井勝さんたちにも取材しました。8時間版で欠けていたピースですね。この3人にはかなり確信犯的に語ってもらっているはずです。
──完成した『映像の発見=松本俊夫の時代』は700分という長さになりました。
 本作に関しては、ロードショー上映しようというような配慮はまったく無く、「とにかく記録しておかなければいけない」という意識で作りました。全五部作で11時間40分。「誰が見るんだ?」と言われるかもしれませんが、僕としてはそれでもいいんです。いまの人が見なくても、後世の人が見てくれればいいという思いもあります。上映時間の3〜4倍の素材がありましたので、構成はかなり施しています。この8月の1週間だけでも、8分足して30分切ったり、という作業もして(笑)。長いと思われる方も、この11時間40分で戦後日本映画史、そして日本の戦後史がわかると考えたらお得かもしれませんよ。そういう自負はあります。もちろんそれは松本さんのこれまでの活動の賜物です。松本さん自身へおこなったインタビューが約15時間。周辺におられた重要な20人ほどの錚々たる方々にも40時間ほど取材しています。松本さんへの最後のインタビューが2011年で、撮り始めてから今年で13年目。ご本人からも、「僕が元気なうちに仕上げてね」と何年も前から言われていたので、約束を守るためにも完成させました。
本作に関しては、ロードショー上映しようというような配慮はまったく無く、「とにかく記録しておかなければいけない」という意識で作りました。全五部作で11時間40分。「誰が見るんだ?」と言われるかもしれませんが、僕としてはそれでもいいんです。いまの人が見なくても、後世の人が見てくれればいいという思いもあります。上映時間の3〜4倍の素材がありましたので、構成はかなり施しています。この8月の1週間だけでも、8分足して30分切ったり、という作業もして(笑)。長いと思われる方も、この11時間40分で戦後日本映画史、そして日本の戦後史がわかると考えたらお得かもしれませんよ。そういう自負はあります。もちろんそれは松本さんのこれまでの活動の賜物です。松本さん自身へおこなったインタビューが約15時間。周辺におられた重要な20人ほどの錚々たる方々にも40時間ほど取材しています。松本さんへの最後のインタビューが2011年で、撮り始めてから今年で13年目。ご本人からも、「僕が元気なうちに仕上げてね」と何年も前から言われていたので、約束を守るためにも完成させました。
──13年間を振り返っていかがですか。
僕が怠け者だったせいで13年掛かってしまったんですが、でもそのおかげで2003年から2011年くらいまでの松本さんを追いかけられた。そのあいだには、お身体を悪くされた時期もあります。そして、取材させていただいた関係者のなかには、悲しいことに、すでに亡くなられた方もいる。本当に悲しいことだけど、撮っていたから肖像を残すことができた。能楽師の観世栄夫さん、脚本家の佐々木守さん。工藤充さんもですね。だから、やはり松本さんのお元気なうちに見てもらいたい思いがあります。
(2015年9月)
取材・文/ラジオ関西『シネマキネマ』吉野大地



