『こどもが映画をつくるとき』
井口奈己監督・増原譲子プロデューサーインタビュー
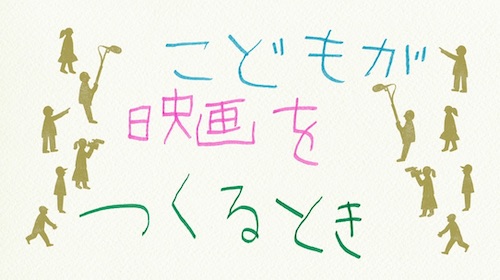
長編では7年ぶりとなる井口奈己監督の新作『こどもが映画をつくるとき』。2020年12月26日から28日の3日間、宮崎で開催されたこども映画教室の様子を捉えた本作は監督初のドキュメンタリーでもある。参加した12名のこどもたちが「別の顔」をテーマに映画を発見してゆく姿を追うカメラは、過去作にない井口映画の別の顔も写し出し、躍動感とみずみずしさの溢れる一作が誕生した。4月14日(水)までYoutubeで限定配信中のこのドキュメンタリーをめぐって、監督とプロデューサーの増原譲子さんにお話を伺った。
──監督とこども映画教室の関係を遡ると、2015年度に金沢で講師をつとめておられますね。
井口 『ニシノユキヒコの恋と冒険』(2014)の宣伝のときに、一度も会ったことがないのにポスター貼りをしてくれたヂョーさん(Yasuo Kamiya)とShinoda Yuliaさんが金沢・シネモンドの上野克支配人と知り合いで、フェイスブック上で仲良くなり、面白い漫画やアニメなどを紹介してもらっていたんです。本当のところは知らないんですけど、上野さんが推薦してくれて講師をやることになったのかなあ? と思ってました。
──そのときの教室はどのような内容だったのでしょう。
井口 好きな映画をそれぞれ1本選んで、そのなかでいちばん好きなシーンを絵に描いて説明する課題を出しました。それからひとりひとりが「その瞬間に気になったもの」の写真を撮ってきて、それをつないで物語を創るというワークをやってから、オリジナルの映画を作ってもらいました。自分が映画を作るときにも「こんな画を撮ってみたい」と記憶に残っている場面を並べていって、その合間にエピソード入れてストーリーにしたりするんですけど、「井口さんのやり方を教えてもらえればいいですよ」ということだったので、自分がやっていることを簡略化して説明するとこんなかな? というやり方でワークショップをしてみました。
──こどもたちの映画をご覧になっていかがでしたか?
井口 衝撃的でした。私は粗野だけど初期衝動があるみたいなものが大好きなので、出来上がった作品を見て、映画って楽しいんだなって思いました。「こんな映画を見せてくれてありがとう」という気持ちになり、2019年に東京のカフェ・タビラコの文化祭用短編映画『だれかが歌ってる』を作れるかもってなったのも、金沢でこどもたちの映画を見たからです。『だれかが歌ってる』はちょっとした偶然をめぐる物語ですが、ラストに公園で遊んでいるこどもたちが本編中に聴こえてくる謎の曲を合唱するシーンがあります。それは長らく大人の歌をこどもたちが歌うっていうシーンをやってみたくてやりました。実際には合唱というか、みんなそれぞれ自由に遊んだり佇んだりしていて、生きてる!って感じがとても良かったので、その経験が本作でこどもを撮ってみようというのにつながった部分があります。
──『だれかが歌ってる』は第26回宮崎映画祭で上映されましたね。
井口 宮崎映画祭は映画を作る度に呼んでくれるんです。いつもすごく応援してくれていて、本作のプロデューサーでもある宮崎映画祭実行委員の臼井省司さんは、見てないのに上映しましょうって言ってました(笑)。「2020年度は宮崎県で第35回国民文化祭が行われるので、そこから予算を引っ張ってきて短編を撮りませんか?」と声をかけてもらったんですけど、コロナが蔓延しはじめていたので宮崎に行くことができなくて……。
増原 『だれかが歌ってる』が完成したのが2019年12月で、短編制作の提案をいただいたのが2020年1月後半でした。
井口 国民文化祭も延期になり、短編映画は作らないんだろうなあって思っていたら、本作のプロデューサーに名を連ねている宮崎文化本舗の石田達也さんが枠組みを変えて予算を取ってきてくれました。そこでひらめいたのが、こども映画教室の開催と、それを撮ることでした。
増原 私たちは宮崎に行けないし、ロケハンやシナハン無しでつくるのは難しい。でもこども映画教室なら3日間で撮れます。宮崎のことをよく知っている方たちと、こども映画教室ならと提案してみました。
井口 宮崎文化本舗の方がこども映画教室に連絡してくださると、「やりましょう」と話が進み出しました。金沢でもチームリーダーをしていた講師のおーちゃん(大川景子)がこどもたちに接する姿を知っていたので、「講師はぜひ大川さんで」とお願いしました。
増原 こちらからお願いしたのはそれだけです。参加者は、宮崎の約60人の応募者から抽選していただきました。
──そうした経緯があったんですね。本作のタイトルコールはこどもの声が重なっています。『ニシノユキヒコの恋と冒険』のラストでも声をダビングされていましたが、あの音処理と関係していますか?
井口 それは無いです(笑)。『だれかが歌ってる』のラストシーンからの流れですね。撮影後、東京に戻ってからメインタイトルの文字を書いてもらい、タイトルコールも録ったんですけど、『だれかが歌ってる』に参加してくれた子たちに声をかけてやってもらいました。
──タイトルの響きは『女が階段を上る時』(成瀬巳喜男/1960)を思い出します。
井口 そういうことにしておきたいですが……(笑)。こどもが映画を作るときに起きる出来事を撮った作品なので、そのままのタイトルにしました。編集に入ってもタイトルが決まってなかったんですけど、タイトルコールの録音が差し迫って来たのでサクッと決めました。
──冒頭のタイトルバックのイラストは、これまでも監督の作品を手がけてこられた芳野さんによるものですね。そこから手持ちカメラで撮られた階段のカットに続き、以降もほぼすべてが手持ちで撮影されています。素早いレスポンスが求められるドキュメンタリーとはいえ、監督の過去作は固定画面を基調にされていたので、これはやや意外でした。
井口 三脚を立てる余裕が全然なくて、いちいち立ててられないんです。こどものほうを見るともう話しはじめていて、待ってくれません(笑)。あと今回はフルセットの撮影隊を連れて行くことができなかったので、撮影の鈴木昭彦さんと真弓信吾さんだけでなく、私と増原さんもカメラを回しました。補助のつもりだったんですけど、どうしても私や増原さんのカメラにしか写ってない場面があって、多少手ブレしていたり、ピントが合ってなかったり、露出が適正でなかったとしても、写っている人が魅力的であればそのカットを使わざるを得ない、という事態になりました。
──『犬猫』(35㎜/2004)DVDの特典メイキング映像を見ると、監督がリハーサルスタジオで主演のおふたりに「カメラの前に堂々といてくれればいい」と語っておられます。今回の現場もそれに似た心構えでしたか?
 井口 今回はカメラを回すだけで、現場で何もしていないんです。こどもたちに話しかけることも一切なく、みんなが映画を作っているのをとにかく撮るだけでした。それぞれの人生を生きている本人たちなので、当たり前なんですけど、全員キャラが立っていて、全員主役みたいでした。フィクションを作るときとはまったく違う感覚でした。
井口 今回はカメラを回すだけで、現場で何もしていないんです。こどもたちに話しかけることも一切なく、みんなが映画を作っているのをとにかく撮るだけでした。それぞれの人生を生きている本人たちなので、当たり前なんですけど、全員キャラが立っていて、全員主役みたいでした。フィクションを作るときとはまったく違う感覚でした。
──4人のカメラの配置はどうなっていたのでしょう。
井口 望遠レンズがひとつしかない事情があり、宮崎神宮(青チーム)には真弓くん、望遠を使う商店街(赤チーム)に鈴木さんが就きました。初日は私が宮崎神宮、増原さんが商店街に行き、2日目はその逆で……。
増原 監督は両方のチームを見たほうがいいだろうということで。
──おふたりはふたつの現場を往復されていたわけですね。
井口 どちらの現場も見ておいて良かったです。その場で感じていた雰囲気みたいなものがあって、編集する時に役に立ちました。
──こどもたちもカメラの存在をまったく意識していませんね。
井口 初日からそうで、撮られることやスマホで撮ることに慣れているのかもしれないですね。あまりにもカメラを意識してないので、微細な心の変化みたいなものが写っているのも編集中には見えました。こどもたちのチームワークが日を追うごとに熟成されてゆくのは面白かったです。お弁当を一緒に食べたあとはちょっと親密さが増していたり、ほとんど初対面で年齢もバラバラな子たちに関係性が芽生えてゆくのはすごいなと思いました。
──1日を昼食で区切る構成案は、撮影の時点でありましたか?
井口 撮っているときはまったく無くて、ただ「撮り逃さないように」とだけ考えていました。ドキュメンタリーを作るのが初めてでよくわかっていない部分があったし、撮影後に「ドキュメンタリーって何ですか?」と知り合いのドキュメンタリー作家たちに訊ねたりもしました。「ドキュメンタリーの監督って何だろう」「現場で何もせずカメラを回していた私は監督なの?」と思ったし、編集の最中もその疑問はずっとありました。
──『犬猫』(8㎜/2001)でデビューされて20周年となる今年、監督にそうおっしゃられると戸惑いますが(笑)、それほど新鮮な試みだったということなのでしょうね。撮影は3日でも、カメラが4台あると編集作業も大変だったかと思います。
井口 まず初日を順番につなぐと、それだけで軽く60分はあって「このままだと3時間を超えるな」と思いました。Youtubeで公開することは決まっていたので、それでは見るのがハードだし、周りからの「え? 3時間……?」という反応もあったりで(笑)、落としていかざるを得ませんでした。
増原 最初は大人の登場部分がもっと多かったんです。
井口 おーちゃんとふかちゃん(赤チームリーダー・深田隆之)以外の大人の気配を落としていきました。それから初日を編集したものを鈴木さんに見せると、鈴木さんが「ここから使うだろう」と思って露出を調整したりピントを送っているポイントの前から全部使っていて「予想と違う。ここを使うのか?」と言われましたね(笑)。
増原 カメラマンは嫌がるだろうなという編集ですね(笑)。
──それはもとの素材がいいことの証明ですよね。輪から外れる子もカメラがフォローしているのも本作の魅力です。
 井口 実は輪から外れる子たちを必要以上にはフォローしてないんですよ(笑)。外れるのはその子たちの内面の事情があって、それは映画を作ることとは別の問題なので、映画に戻って来たらそこにいるってわかるようになっていれば良いなと思って編集していました。
井口 実は輪から外れる子たちを必要以上にはフォローしてないんですよ(笑)。外れるのはその子たちの内面の事情があって、それは映画を作ることとは別の問題なので、映画に戻って来たらそこにいるってわかるようになっていれば良いなと思って編集していました。
──こどもたちの撮った画も本編にいくつか織り交ぜておられますね。
井口 ラッシュを見たときに、みんなが石を投げている池からふわぁっとカメラが移動する画には衝撃を受けました。「すごくいいな。これは入れたい」と思いましたね。
増原 こどもの撮った画と思えなくて「何歳なんだろう」って(笑)。
井口 参加者の撮った映像を入れることで、『こどもが映画をつくるとき』を見た人が、みんなの作った作品を見たくなれば良い、という思いもありました。
──大川さんと深田さんがこどもたちにかける言葉も的確で、そこからこどもたちが様々なアイデアを出し合う姿が見られます。監督は『天然生活』(扶桑社)にエッセイを連載されていますね。最新号では本作がテーマになっていて、池の鯉を撮るためにある子が水中撮影のアイデアを出すシーンに触れておられます。
井口 あのアイデア豊富な子はフィギュアを改造するのが好きらしいですが、映画を好きかどうかは一切訊いていません。あのとき私は現場にいなくて、ラッシュを見て映画的なアイデアを出していることが初めてわかって、シビレましたね。
──読んだあとに本作をふたたび見ると本当にそうで驚くのと同時に、過去の人たちもこうして映画づくりの道を歩んできたのかもしれないと感じました。エッセイにも綴られていますが、現場で見ていたものとラッシュのあいだには大きな違いがあったのでしょうか。
井口 ふたつの違う場所で撮影されていたので、私が全部を目撃したのはラッシュを見たときでした。ラッシュですべてを見ると、そのとき現場で感じたり判断したのとはまったく違うことがおこなわれていたんだなという発見がありました。歩く下駄のシーンを撮るときに、おーちゃんに三脚を水平にする方法を習っていた子が、(三脚を扱ったことのない人は気づかないかもしれませんが)最終日、熱心に三脚を触っているのは水平を取っているんです。2日目に習ったことを最終日に真剣に取り組んでいる姿を見ると「ちゃんと受け取っているんだ」と感動しました。
──あの画は水平出しを捉えていたんですね。さらに大川さんは2日目に「遠くから撮ったものと近くから撮ったものを編集で組み合わせられる」とみんなに教えています。このあたりで画と音を編集することに気づくのかなと思いました。
井口 両チームとも最終日の編集のときに「編集って何するの?」と訊いているので、たぶんまだ気づいてなかったとは思います。でも「音を録ったほうがいいんじゃないか」と意見が出てきます。きっと、その場その場で思い付くんでしょうね。
増原 こどもたちは機材を持ち回りで使っているので、それで必要なものに気づくのかもしれません。
──音への反応も変化していきます。シーンを初日に巻き戻して、商店街で「タナカ」というお店のオーナーがシャッターを下ろすカットがあります。赤チームなので、撮られたのは鈴木さんでしょうか。
井口 あれは増原さんのカメラです。
増原 なぜ撮れたかというと、鈴木さんは次の現場に向かうこどもたちを追っていて、私は残っていたので撮れました。
──あのカットは2日目に起きる出来事の伏線にもなっています。
井口 それも現場ではわかっていなくて、編集中に「タナカの画はない?」と訊くと増原さんが何かムニャムニャ言って、はじめは見せてくれなかったんです(笑)。でもナイスカットですよね。私たちのあいだでは『友だちのうちはどこ?』カットと呼ばれています(笑)。
──言われてみれば(笑)。商店街「文化ストリート」は迷路のようでいい舞台ですよね。それから2日目の後半、宮崎県総合博物館のシーンでは青チームがテイクを何度も重ねます。演出を模索しているようにも、迷走しているようにも見えます。
井口 あそこは編集で少し絞りましたが、博物館に行ったときには既にこどもたちはヘトヘトで、うちのカメラもグラグラの状態になっていました(笑)。でもその様子を入れておかないと、最終日におーちゃんが「もう一度撮影に行こう」と言う理由がわからないので、あのグダグダ感が必要でした。その前から疲れていたのに加えて雨が強くなってきたので、急きょ博物館に撮影場所を提供していただいて撮ることになったんです。
──そこでは、こどもたちが恐竜の化石を見上げて驚く演技がなかなかうまくいきません。
井口 小学6年生の子が最後にみんなで「わぁーっ」で言ったあと、普通に周りに話しかけると全員がやけに自然な演技というか、普通に話しはじめるんです。編集で見ていて、「なぜここは自然になったんだろう?」とすごくびっくりしました。「演技が自然になってるのはなぜだろう?」と(笑)。
──謎の演出効果ですよね(笑)。本作からは、こどもの行動は予測できないことを痛感します。「なぜスタートをかける寸前にそんなことを言うんだ」と驚くシーンもあります。
 井口 あの「マスク取ったほうが良くない?」と言う子は、意見を言うタイミングがズレているのでなかなか伝わらなくて、ずっと自分の気持ちを持て余している様子だったんですけど、常に意志ははっきり伝えていました。最終日に「やっほー」と「カッコー」という声を録ることになったときにやりたい事がすんなり伝わって、見たことのないような満面の笑みを浮かべるんです。我してやったりみたいな(笑)。
井口 あの「マスク取ったほうが良くない?」と言う子は、意見を言うタイミングがズレているのでなかなか伝わらなくて、ずっと自分の気持ちを持て余している様子だったんですけど、常に意志ははっきり伝えていました。最終日に「やっほー」と「カッコー」という声を録ることになったときにやりたい事がすんなり伝わって、見たことのないような満面の笑みを浮かべるんです。我してやったりみたいな(笑)。
──マスクで顔の半分が覆われていても喜びが伝わってきますね。そのあと偶然でしょうが、あの子がフレームアウトするのは監督の映画らしいと感じました。そうして映画づくりが進むに連れてチームワークが高まる一方で、それぞれの個性も際立ってきます。
井口 歩きながら次のカットをどう撮ればいいかと相談してたり、カット割りのイメージを持っていたり、教えていること以上にこどもたちが映画に近づいているという場面もありました。商店街チームが撮影準備でカメラを据えて、縦方向にみんなが走って行ったり来たりしてるのは、まるで大人の撮影現場を見ているようでしたね。私たちの現場もあんな感じで、カメラと待機している役者の間をみんなが走って準備しているんです。
──そのようにひとりひとりが個性を放っていますね。編集の妙技でもあるでしょうが、本作は12人のこどもたち全員が煌めいて見えます。
井口 編集のときに全員にフォーカスできるとわかりました。はじめは、ほかの子たちとは違う行動を取って目立つ子に分量を多く割いたバージョンもありました。でもその行動は映画と関係ないと思って全部落としたんです。落としたあとは、映画に向かい合う姿をもう一度洗い出しました。「映画を作る場に参加したこども」のいいところをつなぐと、それぞれが自分の人生を生きている人だから、全員が主役のようになりました。そしてみんなが一斉に喋ります。そういう映画を編集するのも初めてで、結果的に見るところが多くなりましたね。
──これほど多くの人が画面のなかで声を発している井口作品は初めてですね。ちなみに昼食の様子も撮影されていたのでしょうか。
井口 それは撮りませんでした。私たちもお昼ごはんを食べないといけないし、そこはこどもたちと同じペースで(笑)。
増原 「映画を撮影する姿を撮影する」現場だったので(笑)。
井口 いま思えば、もうひと組、カメラマンと録音技師がいればそういう「外からの映像」も撮れたかもしれないですね。でも最小限の人数で、やれることをギリギリまでやったと思います。
──最終日にみやざきアートセンターに戻り、編集やポスターを制作する様子は固定で撮れる気もしたのですが、ここもやはり手持ち撮影ですね。
井口 大きなスペースをふたつに区切っていて、私たちは分担を決めて行ったり来たりしていたので、カメラを据え置きにはできませんでした。もう一台あれば違ったのでしょうが、据え置いてもこどもたちがそこにいてくれるとは限らない(笑)。
──たしかに(笑)。そのシーンを経て、ラストは上映会の様子を写します。ここを着地点にされた理由は?
井口 完成した映画を上映するまでが、こども映画教室のプログラムです。こどもたちは舞台挨拶や質疑応答もしていましたが、映画の上映がはじまる直前、手で顔を覆い耳をふさぐ子の姿がとてもよかったので、そのカットをラストカットにしました。あの「映画がはじまるぞ」というところで終わらせるのがいいのかなと考えました。見た人たちに「あの子たちの映画を見たい」と思ってもらえるように。
──続けてこどもたちの2作も見たくなる、終わりははじまり的なラストですね。
増原 全体を通して、こどものつくった映画が主役になればいいなとも思いました。
──本作は2021年3月31日にYoutubeで公開されました。いま感じておられることを最後にお聞かせください。
井口 こんなに笑いながら編集したのもはじめてだったし、見れば見るほどこどもたち全員を好きになります。それも現場にいたときとは違う感覚ですね。はじめて映画を作るこどもたちがフレッシュであるのは確実なんですけど、自分たちも、はじめてドキュメンタリー映画を作ったので、こどもたちに恥ずかしくないよう、粗野でフレッシュな映画になるように心がけました。手持ちのカメラで目が回る人はスマホでご覧になることをオススメします(笑)。
(2021年4月2日)
取材・文/吉野大地
●こども映画教室@宮崎映画祭 青チーム『宮崎神宮の自然と音』
●こども映画教室@宮崎映画祭 赤チーム『商店街のふしぎな道』
●こども映画教室公式サイト


